赤ちゃんの頃からやっておいてよかったもの
我が家には9歳の男の子と、5歳の女の子がいます。赤ちゃんのうちからやっておいてよかったことは、今になって気づくものが多い。
もし今、赤ちゃんのうちからやっておいた方が良いことで、悩んでいる人がいたら、育ったらこうなるよ。というのをお伝えしていきたいと思います。
第1位:ベビースイム
私が一番オススメなのは「ベビースイム」。いわゆる水泳です。地元の市民体育館的な場所でやっているものが多く、水着おむつを履いて参加できるので、0歳から始めることができます。
初めのうちは、とにかく水に慣れるところから始めます。まぁ間違いなく泣きますが、水に対する抵抗感は一切なくなるので、お風呂やシャワーで嫌がるなんてことは一度もありませんでした。
子供が育つにつれて、ちゃんとした水泳を習わせるかは人それぞれですが、我が家の長男は、3年生まで水泳を続けました。2年生の時点で、バタフライまで覚えて100mも普通に泳げるようになっていたので、ベビースイムの効果は間違いなくあったかなと思います。
一方で、5歳の長女はベビースイムに通わなかったので、水嫌いにはなりませんでしたが、プールに行っても自力で泳ぐ術を知らないので、なかなか楽しめない様子です。小さいうちから泳ぎは習っておくのがベストかなと思います。
第2位:虫
次に私がオススメしたいのは、「虫」に対する抵抗感をなくしておくことです。大人の中にも虫嫌いは多くいるかと思いますが、子供は親を見て育ちますから、虫が気持ち悪いものと印象付けられてしまうと、なんとなく子供も虫嫌いになっていきます。
我が家の場合、母親が虫を得意としていたので、小さい頃から色んな虫を捕まえては持って帰っていました。中には、ニジイロクワガタやヘラクレスオオカブトを購入して育ててみたりもしました。結果、子供2人とも虫は全く怖がらず、外に出れば手ぶらで帰ってくることの方が少ないほどです。
私のような虫嫌いにとっては、家に大きめの虫が出た時など、子供が素手でスッと取ってくれるという大きなメリットがあります。ただ、家に帰ると日に日に虫かごが増えている場合があるので、ある意味虫に囲まれた生活を余儀なくされる可能性もあります。
第3位:オムツ(の卒業)
3つ目は「オムツを早めに卒業すること」です。オムツを取る練習は自宅でしなければならないため、両親が忙しいとなかなかできません。
子ども自身、周りのお友達がパンツを履き始めるのを見て、モヤモヤすることもあります。また、もし自宅にオムツ用のゴミ箱がある場合は、あの独特の強烈な匂いから早く解放されるためにも、頑張って早めにオムツを卒業しましょう!
初めのうちは、頻繁に「トイレは大丈夫?」と聞きながら、出なくても良いからトイレに行ってみようと勧めながら練習すると意外に早く卒業できます。
夜寝る前に必ずトイレに行かせておくのが重要です!ちゃんと出来たらその都度褒めてあげるのも大事です!
第4位:料理(のお手伝い)
小さい頃から料理の手伝いをしておくと、作ってもらうありがたさを感じるようになり、好き嫌いや食べ残しが少なくなります。
例えば、卵を割る係や混ぜる係から始めると、大きくなるにつれて、自発的に手伝いたがるようになります。個人的には、味見係に任命したところ、その料理はだいたい食べてくれますし、食べたことのないものへの抵抗感も少なくなるように思います。
家での遊びの一つに料理が増えるので、非常にコスパがいいなと感じています。
第5位:英語
子供が小さいうちは、物覚えも早いので、早めに英語に触れておくことで、ネイティブな発音に近い英語を習得します。例えばアニメ(我が家ではスポンジボブやペッパーピッグなど)を英語版で見たり、ゲーム感覚で遊べるアプリも豊富にあるので、ただyoutubeを見せるよりは有効的かなと思います。
ただし、忘れるのも早いので、我が家の長男は少し英語から離れただけであっという間に忘れ去りました。おそらく、継続することが大事なんだと思いますが、英会話に通わなくても、英語のコンテンツに触れておくだけでも十分です。
長女はまだ5歳ですが、英語っぽい日本語を話しながら、英語もさらっと言ったりするので、小さいうちから日常に英語がある環境を作れたらそれがベストかなと思います。
まとめ:赤ちゃんからやっておいた方が良いもの
小さい頃から続けることで、色んなものを習得できるのが子供です。
ただ一番大事なのは、「強要しないこと」です。子供の「楽しい」という感覚を邪魔しないように、裏で環境を整えることが親としてできることかなと思います。
色々経験させてみて、本人がハマったものに焦点を当てていくのが良いかなと思います。

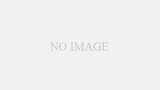

コメント